帯広地区学校説明会を開催いたします。
本校の教育理念や進路、高校生活、寄宿舎の生活等について説明します。
また、学校生活や入学試験等に関する個別相談も実施します。
ぜひお気軽にご参加ください。
9/30(日)10:00~11:00
会場/とかちプラザ
帯広市西4南13
TEL/0155-22-7890
帯広地区学校説明会を開催いたします。
本校の教育理念や進路、高校生活、寄宿舎の生活等について説明します。
また、学校生活や入学試験等に関する個別相談も実施します。
ぜひお気軽にご参加ください。
9/30(日)10:00~11:00
会場/とかちプラザ
帯広市西4南13
TEL/0155-22-7890
釧路地区学校説明会を開催いたします。
本校の教育理念や進路、高校生活、寄宿舎の生活等について説明します。
また、学校生活や入学試験等に関する個別相談も実施します。
ぜひお気軽にご参加ください。
9/29(土)14:00~15:00
会場/釧路市生涯学習センター(まなぼっと幣舞)
釧路市幣舞4-28
TEL/0154-41-8181
姉妹校では3年に1度実施される「富士登山」に今回は総勢44名の生徒が参加し、札幌聖心からは3名が登山にチャレンジしました。 初日、6班に分けたパーティーは、富士宮口ルートの5合目までバスで移動し、一般登山客で混雑していましたが、雄大な景色を眺めながら一歩一歩登りました。夕方に8合目の山小屋「池田館」に到着し、雲海の大パノラマはまさに絶景そのものでした。翌深夜1時30分からゆっくりと山頂を目指し、ついに頂上にゴール!4時45分頃に神々しく光を放つ「ご来光」にみな感動いっぱいの瞬間でした。
参加者は初めての富士登山を体験し、体力と忍耐力が鍛えられ、1つの目標を成し遂げる達成感を味わいました。また、姉妹校の仲間との新しい絆を深めることができ、大変有意義な2日間となりました。





24日火曜日の二日目は、難民を助ける会を訪問しました。
難民とはどういう状況に身を置いているか、またその人一人ひとりに個別の事情があることを
想像しながら、「あなたならどうするか?」というディスカッションを行いました。
その日の午後は、宿舎で振り返りと分かち合いの時間をとりました。
それぞれの場所で聞いてきた内容のすり合わせや、新たにわいてきた疑問などについて
まとめていきました。また、自分たちの経験を、同級生をはじめ多くの生徒たちと共有をする使命を果たすため、
どんな内容をどのようにまとめたらよいかという話しあいも行いました。
夜は、この春に卒業した大学1年生3人が遊びに来てくれました。
大学生活の事や、高校生活でのアドバイスなど、楽しくためになる時間を過ごしました。
最終日は東京入国管理局を訪問しました。難民の定義から始まり、日本の難民受け入れの姿勢やその方針についての
お話を詳しく伺うことができました。いろいろな立場から一つの物事を見ることの大切さに気づく時間でした。
どの団体の方もいつも忙しい中、時間を割き、対応してくださっていることに感謝の気持ちでいっぱいです。
10月5日(土)に研修の発表報告が待っています。参加した生徒たちは、人との共生のために私たちができることが
何かを考え、多くの人にシェアしていけるように準備を進めていくことと思います。
改めて、この研修に携わってくださった各団体の皆様をはじめ、全ての方々に感謝申し上げます。




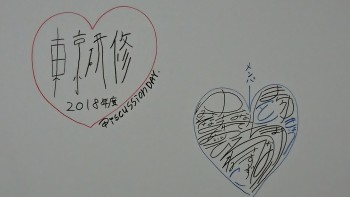



7月23日(月)~25日(水)まで、高校1年生10名は、SGH東京研修に行ってきました。
猛暑の中、4団体を3日かけて訪問する研修も、早いもので4回目を迎えました。
テーマは、貧困で教育や生活に困難がある人の支援と、紛争や様々な事情により難民となった
人々に対する支援についてです。
1日目はチャイルド・ファンド・ジャパンを訪問しました。
1990年代からずっと支援を続けているフィリピンの子どもたちも、4人を数えます。
今支援しているライサさんの映像を見せていただきました。10年近く支援している彼女の
生の声を初めて耳にした感激の時間でした。
その後、難民支援協会を訪問しました。
新しい事務所に移転したばかりでした。難民申請中の人々のために、プライバシーを尊重し、
本当に必要な支援ができるようにと作られた施設を見学させていただきました。
報告②に続きます。







